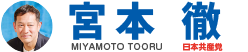2015年3月11日 衆院財務金融委員会 研究開発減税 大企業ばかりに恩恵 社名公表を要求
(以下、「しんぶん赤旗」記事)
日本共産党の宮本徹議員は11日の衆院財務金融委員会で、研究開発減税の適用総額に占める大企業の割合の推移を示し、大企業ばかりが恩恵を受ける不公平税制を改めるよう求めました。
宮本氏が示した資料によると、2013年度の研究開発減税額は6240億円にのぼり、そのうち92%を大企業が適用を受けています。宮本氏は「一部巨大企業に巨額の補助金が渡っているに等しい」と述べ、減税額上位10社の社名を公表するよう求めました。麻生太郎財務相は「(減税の原資は)国民負担」と認めましたが、企業名の公表は「慎重な検討が必要」と答えました。
さらに宮本氏は、昨年6月の政府税調報告では研究開発減税の「大幅な縮減」が明記されていたのに、経団連が「現行制度を維持・拡充すべきだ」との提言を発表すると方針を転換し、2年限りの優遇措置を恒久化する法案まで提出していると指摘。「『縮減』どころか『拡充』になっている。経団連の要望通りではないか」とただしました。麻生財務相は「関係者と議論を重ねた結果、今回示した結論を得た」と述べ、経団連側の意見を取り入れたことを認めました。
宮本氏は「中小企業に配慮しながら、研究開発減税を大胆に縮減すべきだ」と主張。「法人税率引き下げ、大企業優遇を続けながら、消費税増税と赤字企業への増税で穴埋めするなど許されない」と批判しました。
≪189回 財務金融委員会4号 2015年3月11日議事録≫
○古川委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。所得税法等の一部を改正する法律案について質問いたします。きょうは、まず、研究開発減税について伺います。本会議で、私は、消費税増税はやめ、大企業優遇税制こそ見直すべきだと求めました。租税特別措置の中で大企業優遇の最大のものは、研究開発税制となっております。研究開発減税の適用総額と、資本金十億円以上の企業が占める比率について、今世紀初めの二〇〇一年度と二〇一三年度について、それぞれ幾らになっているのか、お伺いします。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。お尋ねの研究開発税制に関しますデータでございますが、二〇〇一年と二〇一三年度、こういうことでございます。若干申し上げますと、十年たっておりますので、制度がかなり変わっております。それから、サンプルといいますか、このデータのとり方も大きく変わっておりまして、二〇〇一年当時は国税庁の会社標本調査というものによっておりましたが、現在は租税特別措置の適用実態調査によっているということですので、その制度もかなり違う、そういう前提でお聞き取りいただければと思います。まず、二〇一三年度、足元でございます。租税特別措置の適用実態調査によりますと、適用総額が全体で六千二百四十億円、それに対しまして、資本金十億円超の法人及び連結法人の割合は九一・八%ということでございます。他方、二〇〇一年でございますけれども、これは今申し上げました国税庁の会社標本調査に基づいたデータでございますが、適用総額七百七億円、資本金十億円以上の法人の割合は六四・六%となってございます。
○宮本(徹)委員 今お話ししていただいたとおりですけれども、私、きょう、提出資料を、二つの統計をつなぎ合わせてつくったものを出させていただきましたが、二〇〇三年度の税制改正で、財界が要望する法人税率引き下げのかわりに、新たに研究開発減税の総額型を設けたのを機に、減税額が一千億円を超え、その後、急増していくということになっております。そして、減税の恩恵も資本金十億円以上の企業にどんどん集中してきているというのが、このグラフからも明らかということだと思います。減税の恩恵の大半を一握りの大企業が受けているのが、この研究開発減税の制度です。減税総額は、二〇一二年度は三千九百五十一億円でしたから、一年で一・六倍、二千二百八十八億円も減税額がふえていることになります。二〇一二年度から二〇一三年度にかけて、研究開発減税の減税額がふえた制度上の原因は何でしょうか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。御指摘のように、二〇一二年度から二〇一三年度にかけまして、研究開発税制の適用総額が二千億強伸びてございます。その制度要因といたしましては、平成二十五年度改正におきまして、いわゆる総額型の控除限度額が、法人税額の二〇%というものから法人税額の三〇%に上乗せをされたということがあろうかと思います。加えて、恐らく、この時期、景気回復局面で、企業が投資を活発にしているといった事情も手伝っているのかなというふうに思います。以上でございます。
○宮本(徹)委員 景気回復の影響もあると思いますが、同時に、総額型の控除限度額を、上限を二〇%から三〇%に一・五倍に大きく引き上げたことが、減税額をふやす大きな要因となっております。さらに、二〇一四年度はまだ出ていないわけですけれども、二〇一四年度も、研究開発減税は二百七十億円積み増すという税制改正を行っているわけであります。二〇一三年度の研究開発減税の減税額上位十社の減税額の合計と、十社が減税額全体に占める割合は幾らになっているでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。平成二十五年度の租税特別措置の適用実態調査に基づいた数字でございます。研究開発税制適用額上位十社の合計額が二千五百五十三億、適用総額が六千二百四十億でございますので、その比率は四〇・九%ということでございます。
○宮本(徹)委員 四〇・九%ということで、十社で減税額全体の四一%も占めているということになります。きのうの委員会の質疑の中でも、佐藤主税局長が、研究開発減税については一種の補助金だというふうに発言されておりましたが、一部の巨大企業に巨額の補助金が渡っているに等しい状況になっています。研究開発減税は、本来国庫に入るべき税金を特別に減税しているわけですから、この原資は国民の税金だということを確認したいんですが、麻生大臣、どうでしょうか。
○麻生国務大臣 研究開発税制による、法人税収が減収となったと言われている部分ということになるんだと思いますが、それは国民負担により賄われているということだと存じます。この研究開発税制の利用によって企業が研究開発投資というものを活発に行うことになれば、それが結果として技術革新につながり、成長の原動力になっている面もあるんだ、我々はそう考えておりますので、こうした政策効果について考慮に入れて予算というものは編成されてしかるべきものだと考えております。
○宮本(徹)委員 麻生大臣からも、国民の負担により賄われているという答弁がありました。私は、国民の税金を原資にして減税している以上、巨額の減税を受けている企業名は公開されてしかるべきだというふうに考えます。ところが、適用実態調査の報告書には、上位十社のコード番号しか書かれておりません。麻生大臣、これは国家機密なのでしょうか。
○麻生国務大臣 今御指摘のあっておりました租特の適用実態調査の報告書におきましては、租特の利用状態を明らかにして政策の企画立案に役立てていくことを目的としておりますから、こうした目的に照らして、個別企業名まで公表する必要はないという整理が平成二十二年の立法当時からなされておりますのは御存じのとおりです。一般論として、仮に国が個別企業の納税情報の公表ということになりますと、対象となります企業におきましては、価格交渉への影響、また競争上の不利益等々が生じかねないことから、それを十分に上回る公益上の必要があるかどうかということの上から、我々は慎重な検討が必要であろうと考えております。
○宮本(徹)委員 国民の目からすれば、これほどの巨額な減税が行われているわけですから、さらに透明化されてしかるべきだというふうに思いますし、もともとこの法案をつくる過程では、企業名を明らかにしようという議論があったというふうにも聞いております。一位の一社で一千二百億円もの減税ということになっております。今回の予算案では、介護報酬の切り下げ、それから生活保護の切り下げがあります。この二つを合わせたら一千二百億円ということになります。ですから、削るところが全く間違っているんじゃないかというふうに私たちは思っております。私たちの機関紙のしんぶん赤旗が有価証券報告書と照らし合わせて試算したところ、一位の会社はトヨタだと判明いたしております。しんぶん赤旗がトヨタの広報部にも確認しましたが、トヨタの広報部は、納税額の内訳については開示していないので答えられませんと述べましたが、否定はしませんでした。麻生大臣、この減税額第一位はトヨタですよね。
○麻生国務大臣 先ほども申し上げたので、同じことを聞いておられるのだと存じますが、租税特別措置の適用実態調査の報告書に掲載をしております各租特の適用上位十社について個別企業名は公表していない、したがいまして、研究開発税制の適用額の第一位の企業についてもその内容は同じことであろうと存じます。
○宮本(徹)委員 先ほども言いましたように、やはりその企業名を国民は知る権利があると私たちは考えております。週刊ポストの三月六日号には、富岡幸雄中央大名誉教授が有価証券報告書などから試算して明らかにした、研究開発減税の減税額が多い十社が出ております。トヨタ、武田薬品、デンソー、キヤノン、NTT、JR東海、第一三共、NTTドコモ、小松製作所、田辺三菱製薬と、名立たる大企業が並んでおります。私たちの党内でも調査した方がいらっしゃいます、これと若干違う企業名が入っていたりもしますけれども、そのケースの場合は。どちらにしても、有価証券報告書をめくれば一定のことはわかるわけですけれども、めくらないとわからないというのは本当におかしな話だと思うんですね。調べれば一定のところまで調べはつくわけですから、上位十社の企業名の公表ぐらい、ぜひ大臣の決断でやっていただきたいというふうに思いますが、重ねてお伺いします。
○麻生国務大臣 重ねてお答えいたしますが、国が特別措置、いわゆる租特の適用状況に関する個別企業の情報を公表することにつきましては、研究開発税制の適用額が大きい企業に対象を絞ったといたしましても、企業イメージの影響などを含め、競争上の不利益が生じかねないのではないか、また企業側の理解が得られぬまま公表に踏み切れば税務当局への信頼や協力が損なわれないかなど、いろいろな点について慎重な検討が必要であって、研究開発税制の適用上位十社の企業名について公表するつもりはございません。
○宮本(徹)委員 企業イメージということを言われますけれども、国民も物すごく関心を持っているわけですね。週刊誌のつり広告になって発表されるようなことになっているわけですよ。公表しないことが逆に企業イメージを損なっていることになるんじゃないかというふうに思います。私、調べてみましたら、トヨタから自民党の政治資金団体である国民政治協会への献金は、二〇一二年の五千百四十万円から、二〇一三年は六千四百四十万円にふえているということであります。研究開発減税がふえると同時にふえているわけであります。ですから、事実上、減税分が自民党に還流しているというのと、構図としては、今、政治と金で補助金の問題になっているのは同じ構図だというふうに思います。これを公表しないのは、こういう関係を隠したいんだというふうに批判されても仕方がないんじゃないかというふうに思います。私たちは、研究開発減税は、中小企業への配慮は当然行いながら、大幅に縮小すべきだということを主張してまいりました。先ほど、政策効果も見てくれということを麻生大臣はおっしゃいましたけれども、研究開発減税を縮減しても企業の研究開発には大きな影響を与えないということも政府の調査で明らかになっております。経済産業省が委託調査で行った、研究開発税制の利用状況及び経済波及効果に関する調査の報告が昨年二月に発表されております。二回アンケートを行っております。その中で、平成二十四年度税制改正における研究開発減税の縮減による影響という項目があります。この平成二十四年度の税制改正のときは、総額型の控除上限が三〇%から二〇%に下がったときですが、その影響を聞いているわけですね。アンケートの結果はこうです。必要不可欠な投資として継続すべきだから影響はなかった、六一・九%。全体で法人税額は減少するので影響はなかった、一五・〇%。一方で、研究開発投資が減少したというのは一・四%ということになっております。研究開発減税で研究開発への投資が進むんだということを言われるわけですけれども、政府自身が行った委託調査でも、研究開発減税を縮減しても影響はほとんどなかったということでありました。企業自身は、競争の中で生き残りをかけて研究開発はしっかり行っていくということだからだと思います。そこで、昨年六月に政府税調がまとめた「法人税の改革について」がありますが、これを見ますと、研究開発税制の総額型についてはこう書いてあります。税率の引き下げに対応して大胆に縮減すべきであるとなっておりました。また、対象となる試験研究費についても、人件費、減価償却費や外部委託費などの算入を制限している諸外国の例も参考としつつ、対象の重点化を図るべきとされておりました。そこで、お伺いしますが、現在の研究開発税制の法人税額の控除額の上限はどうなっているのか、そして、法改正が仮になければ、来年度、再来年度、そしてその先と、どうなっていくのか、お答えください。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。研究開発税制の控除限度額でございます。研究開発税制は三種類ございまして、総額型、増加型、高水準型とございます。これらをまとめてということでお話をさせていただきますが、現在のところ、総額型につきましては法人税額の三〇%でございます。加えまして、増加型または高水準型につきましては法人税額の一〇%ということでございますので、合わせまして、現時点では最大四〇%ということになってございます。それから、今お尋ねがございました、仮に税制改正を行わなければという仮定のお話でございますけれども、それを機械的に落としますと、本年度末、二十六年度末には、総額型の控除限度額の上乗せ分、二〇%から三〇%に上乗せしているこの一〇%分が適用期限が参るということでございますので、それを踏まえますと、二十七年度以降は、総額型については法人税額の二〇%、増加型、高水準型を合わせまして、全体として法人税額の三〇%となります。それから、増加型、高水準型についても、実は平成二十八年度末にまた適用期限が参りますので、仮に二十九年度以降これらを廃止するということになりますと、総額型のみが残るということになりますので、法人税額の二〇%というふうな流れになるということでございます。
○宮本(徹)委員 今御説明がありましたように、つまり、現在、税額の四〇%という控除額の上限が、法改正がなければ、この四月からは総額型の二〇%プラス増加型などの一〇%を加えての三〇%、さらに、二〇一七年度からは二〇%に下がるということであります。ところが、今回の法案では、本来総額型は二〇一五年から二〇%になるはずだったものを、上限を三〇%に引き上げて、しかも、これまでのように期限を区切るというやり方ではなく、恒久措置にしております。昨年六月の政府税調の報告を先ほど紹介しましたように、総額型は大胆な縮減を検討すべきというふうになっていたわけですが、これでは、大胆な縮減どころか、事実上の拡充になっているんじゃないでしょうか。
○麻生国務大臣 昨年六月に政府税制調査会が法人税改革に関して取りまとめた報告書、今言われましたが、このうち、研究開発税制のうち総額型の税額控除については、もともと平成十五年度の税制改革において、法人税率引き下げが見送られる中で導入された経緯というものを踏まえて、今回の法人税改革の中で、税率引き下げにあわせて大胆に縮減すべきと提言されておる、今お話があっておるとおりです。二十七年度税制改正におきましては、総額型の税額控除の上限枠を中心として検討を行わせていただきました。税額控除の上限の総枠は現行の法人税の三〇%を維持しつつも、一般の研究開発につきましては、上限枠を五%圧縮して法人税額の二五%とし、他方で、共同研究などいわゆるオープンイノベーション型の研究開発につきましては、上限枠を別枠化して、法人税額の五%として、こちらに支援の重点をシフトするなどの見直しを行っております。このように、今回の見直しは、一般の研究開発の上限枠を圧縮するなど、研究開発税制の縮減と評価できるものであって、一定の増収が見込まれることから、縮減どころか拡充になっているという御批判は全く当たらないと存じます。
○宮本(徹)委員 全く当たらないという批判ですが、法改正しなければ、先ほど説明があったとおり、二〇%に下がるところだったわけですよ。それを、二五プラス五の三〇%にしているというのは、これは事実上の拡充じゃないかということを言っているわけであります。なぜ政府税調が言っていた総額型の大胆な縮減がなされなかったのか、そこにはやはり経団連の要望があると思っております。昨年九月、経団連が、平成二十七年度税制改正に対する提言を出しております。その中で、研究開発税制についてはこう言っております。「平成二十六年度末に期限を迎える税額控除限度額の時限的引き上げ措置(法人税額の二〇%から三〇%)や研究開発費の範囲も含め、現行制度を維持・拡充すべきであり、競争力強化に資するものは、本則で措置すべきである。」という要望を出しているわけであります。麻生大臣、結局、経団連の言っているこの要求に応えて、政府税調が当初言っていた大胆な縮減という結論がひっくり返って、私の言っている事実上の拡充、つまり、総額型の控除額が、上限が二〇%に戻らずに、三〇%が恒久化されるということになったんじゃないでしょうか。
○麻生国務大臣 法人税の改革の具体案を検討していく際に、財界の方にも課税ベースの拡大等による財源確保への協力を求めるため、さまざまなレベルでの議論を重ねてきたところです。御指摘の研究開発税制につきましては、先ほども申し上げましたが、昨年六月の政府税制調査会の報告において税率引き下げにあわせて大胆に縮減すべきとされておりますが、他方で、昨年の九月に公表されました経団連の二十七年度税制改正に関する提言では、現行制度を維持拡充すべきともされておりまして、これはさまざまな議論がなされておりますのは確かであります。こうした点につきましても、関係者において議論をいろいろ重ねた結果、与党における議論を経て、今回お示ししたような結論を得たというところであります。
○宮本(徹)委員 今お話があったとおり、経団連の皆さんから要望をいただいて、結局、政府税調の結論がひっくり返ってしまったということだと思います。私たちが聞いたところでは、当時の自民党税調では、研究開発減税の総額型の控除限度額については二つの案が示されていたというふうに聞いております。その一つには、原則である総額型の法人税額の控除額の上限は二〇%にするという案も示されていたということです。なぜこの案にしなかったのかと思います。また、自民党税調では、研究開発減税の総額型について、適用期限を二〇一六年度末に設定してはどうかという提案もされていたというふうに聞きました。もしそれをやっていれば、それこそ二〇一六年度末で研究開発減税の総額型をやめて、そうなれば文字どおり大胆な縮減ということになっていたと思うんですね。ところが、この提案も、議論の中で採用されなかったということであります。本当に経団連の言うとおりになってしまったということだと思います。税務弘報という雑誌の三月号で、経団連の常務理事の阿部泰久さんが、二〇一五年度の税制改正の裏舞台について一部語っております。ちょっと長いですが、紹介いたします。毎年の税制改正に当たり、法人税法案については、財務省が中心となり、あとは納税者代表として経団連が意見を出しています。検討過程では、経団連主要企業データと突き合わせてシミュレーションを行って、どれだけ制度を変えたら企業にどれだけ影響があるのかというのを当てはめていきます。研究開発減税については、こう言っております。問題になっていたのは、控除限度額の法人税額の三〇%を本則二〇%に戻すかという話で、一度は二五%という中間の数字で決まりかけたのですが、試験研究費については維持したいという意見があり、結局、今、総枠の中に入っているのを別枠に取り出して、それに五%の控除限度額をつけるということになりました。そうすると、二五プラス五で限度額は三〇のままだということになるわけですということで、自分たちと相談して、維持してもらったんだということを述べております。そして、税制改正全体としてはこう言っております。税率だけ引き下げても、企業の負担が減らないのでは困ります。今回は先行減税になっていますが、とにかく実質減税を確保するということが大前提として目指されています。先行減税分は二年間で二千百億円という数字になっていますが、必要最小限という印象ですね。あえて点数をつけるなら八十点ぐらい、合格点かなという印象がありますというふうに述べられております。税率は引き下げろ、課税ベースの拡大を言おうとしたらそれは縮小しろ、研究開発減税は拡充しろと。本当に、私たちからすれば傍若無人な、財界の側の要望はどんどん出して、そして庶民には消費税増税だということであります。結局、本当に、財界の要望を聞いて、こういう道をどんどん進めて庶民に負担をかぶせていくのは問題だというふうに思います。そして、中小企業への配慮は当然必要ですが、私自身は、政府税調も言っていた、研究開発減税の大胆な縮減に取り組んでいかなければならないというふうに考えております。本会議で私、この点を質問したところ、安倍総理からは、「引き続きさまざまな観点からその取り扱いについて検討してまいります。」という答弁がありました。麻生大臣、総理の言われたこの「さまざまな観点」という中には、大企業優遇を正して研究開発減税をさらに縮減していくんだという観点は入っているんでしょうか。
○麻生国務大臣 法人税の改革につきまして、二十八年度以降の税制改正において、課税ベースの拡大などを行いつつ税率を引き下げるということにしております。総理も本会議で御答弁をされておりますように、研究開発税制につきましても、経済の好循環の定着状況などを踏まえつつ、引き続きさまざまな観点からその取り扱いについて検討していく考えであるということを言われております。なお、研究開発税制につきましては、大企業優遇を縮減する観点からの検討を行うのかというお尋ねもありましたけれども、研究開発税制というのは、金額ベースで見れば大企業の利用が多くなっている一方で、件数ベースで見ますれば中小企業の利用が大企業の利用件数の約二倍になっております。もう御存じのとおりだと思いますので、必ずしも大企業だけが優遇されている状況にはなっていない、私どもとしてはそう考えております。
○宮本(徹)委員 ですから、私自身も、中小企業には当然配慮しながらこの税制の見直しが必要じゃないかということを先ほどから申し上げているわけであります。お答えがなかったんですけれども、研究開発減税を縮減していくという観点は、今後のさまざまな検討をする観点の中には入っているんでしょうか。
○麻生国務大臣 先ほど申し上げましたように、さまざまな観点から検討するとお答え申し上げました。
○宮本(徹)委員 何か禅問答のようで、それ以上質問してもあれなので、次に行きます。今回の法案では、研究開発減税の総額型での控除限度額三〇%というのは、二年限りの時限措置が、期限なしということで三〇%ということになっております。私は、恒久化というのは、これまた政府の税制調査会の言っていることとも違うというふうに思います。政府税制調査会の「法人税の改革について」は、租税特別措置の見直しの基準について、「基準一 期限の定めのある政策税制は、原則、期限到来時に廃止する」「基準二 期限の定めのない政策税制は、期限を設定するとともに、対象の重点化などの見直しを行う」ということになっているわけです。これに反して、期限があったものを、期限を今回なくしてしまったわけであります。これは麻生大臣にお伺いしますけれども、この総額型だけで三〇%もの税の控除を、今後、未来永劫続けるおつもりなんでしょうか、それとも引き下げていくことはあるんでしょうか。
○麻生国務大臣 研究開発税制について、二十七年度の税制改正では、総額型の税額控除の上限枠を原則の法人税額の二〇%から三〇%へと上乗せする特例が期限を迎えるということから、一般の研究開発の上限枠を二五%とするなどの見直しを行ったところであります。これによって一定の改革が実現したものと考えておりますが、現時点で具体的なアイデアでこうするというわけではありませんが、今後、総額型のほか、増加型、いわゆる試験研究の増加額の一定割合を税額控除するというような増加型とか、高水準型、売り上げの一〇%の試験研究費の額の一定割合を税額控除するといったような高水準型も含めた研究開発税制全般にわたってさまざまな観点から検討を行っていきたい、いろいろ考えておるところであります。
○宮本(徹)委員 増加型、高水準型とあわせて、総額型も含めて検討を行っていくということですから、政府税調にも反するような方向で、政策減税の期限の設定をなくしちゃったというのは直ちに見直していくことが必要だというふうに思います。次に、受取配当の益金不算入制度について質問いたします。財務省の法人企業統計調査によると、今世紀初めの配当金の総額は四兆四千九百五十六億円でした。その後、配当性向がどんどん高まる中、二〇一三年には配当金の総額は十四兆四千二億円ということで急増しております。当然、これに伴って、企業が保有している株式から受け取る配当も急増しております。益金不算入額も急増しているということになります。受取配当の一部を益金に算入する制度が始まったのは恐らく一九八九年だったかと思いますが、この一九八九年と直近の二〇一二年度について、受取配当の益金不算入額の全体の額、また、そのうち資本金百億円を超える法人、巨大企業が占める割合についてお答えいただきたいと思います。
○佐川政府参考人 お答えします。国税庁の会社標本調査におきまして、受取配当の益金不算入額の合計額でございますが、今おっしゃいました一九八九年度は八千百七十九億円、それから二〇一二年度は七兆四千四百八十二億円でございます。また、一九八九年度におけます益金不算入額のうち、資本金百億円以上の法人に係る額の割合は六〇・二%、また、二〇一二年度におけます益金不算入額のうち、資本金百億円超の法人で連結法人を除いたものの額の割合が四〇・五%、連結法人につきましては四六・五%で、その両者を足しますと八六・九%となります。
○宮本(徹)委員 今お話にありましたように、この間、益金不算入の額は約九倍に大きく膨れ上がっているということになります。そして、資本金百億円の企業が占める割合も、六〇・二%から八六・九%ということでどんどん高まっている。この制度も、大きな傾向として、制度の恩恵を受けるのが巨大企業にどんどん集中しているということが言えると思います。私、きょう、提出資料として、この間、全体で益金の不算入額はどうなっているのか、資本金百億円を超える企業と連結法人の占める割合がどうなっているのかというのをグラフにしましたが、この緑のラインも、大きな傾向として、どんどん高まっているという傾向があります。配当がふえればふえるほど、受取配当の益金不算入の制度による減収も大きくなっております。そして、国の税収に穴をあけるということになっております。麻生大臣もこの間、繰り返し、企業が内部留保をため込み続けているのは問題だという認識をおっしゃって、賃金に回しなさい、投資に回しなさいということを表明されています。その点は私たちも全く同じ思いでありますが、この受取配当の益金不算入制度を利用すれば、企業グループでも、株をお互い持ち合えば、各企業の配当金を、ほとんど税金を支払わないまま内部留保にしていくことが可能になっていくわけであります。大臣にお伺いしたいんですけれども、この受取配当の益金不算入制度というのは、大企業が内部留保をふやす一つの要因になっているんじゃないでしょうか。
○麻生国務大臣 予算委員会でも、またここでも申し上げましたけれども、一年に一遍しか数字は出ませんので、おととしの三月で約三百四兆円の内部留保が、去年の三月で三百二十八兆円、年間で二十四兆円ふえておりますので、月割り二兆円という増額になっておることに関しては問題ではないかということを申し上げておりますので、この点に関しては、珍しく意見が合っております。このため、我々としてはどうするかといえば、これはコーポレートガバナンスという、余り好きな言葉じゃありませんけれども、内部できちんとした形のものをやらないかぬということの強化とか、また政労使会議、これもちょっといかがなものかと思いますけれども、非常時であるということで、政労使会議ということもさせていただきましたよ。そして、少なくとも、今度の中においていろいろな意識というものを、企業として、二十年間もデフレをやっているんだから、金をずっとため込んでおきさえすれば、金利がつかなくても、物が下がって金の値打ちが上がるという状況が二十年も続きましたから、ある程度意識が変わるまでに時間がかかるとは思いますけれども、私どもとしては、こういったようなことは今後きちんとした形で配当もしくは賃金、設備投資といったことに回っていくようにしていただかないといかぬということだろうと思って、スチュワードシップ・コードなど、いろいろな形でこの問題に関して対応させていただきつつあります。受取配当金の益金不算入の話、非課税を認めている話で、手元流動性が過剰に残ることになっておるのではないかという御懸念ですけれども、益金不算入の制度というものは、配当を支払う法人、例えば親会社から見れば子会社の段階で既に法人税は課せられていますから、したがって、もう一回取る二重課税ということを避ける観点から、配当を受け取る本人、例えば親会社の段階で税負担を調整するということとしているものであります。仮に、その会社を支配するという目的で保有しております持ち株比率の高い会社からの配当を益金算入にしたとしても、企業は今度は支店形態を選択して二重課税を避ける、手元に資金が残る可能性がありますので、益金算入にしても御懸念は解消しないものだと私どもは考えております。また、内部留保を有効に活用するという観点からは、今回の法人税改革などによって企業の意識や行動を変えていくというところが一番大きな問題なのであって、この意識が変わらない間は、法律で幾らやっても、それは何だかんだ、企業経営者の一番の問題はそれをどう活用するかという意識の問題だろうと思っておりますので、私どもは、その点は、今後ともいろいろな形でこの問題について対応していかねばならぬと思っております。
○宮本(徹)委員 内部留保は設備投資、賃金、配当に回らなきゃいけないということを言いますけれども、その配当は、内部留保として、益金不算入制度を使ってまた戻ってくるという仕組みにもこの制度によってなっているわけであります。この制度は、当初、おっしゃるとおり、二重課税を廃止するために設けられたということは聞いておりますけれども、同時に、実態に即して修正を加えて、一部は益金に算入するということもこの間やってきた経過があります。私は、やはり税の本来の役割というのは、所得の再分配というところにあると思います。この原点に立ち戻って、この受取配当益金不算入制度はさらに見直していく必要があるんじゃないかというふうに考えております。先ほどの麻生大臣のお話にあるとおり、内部留保は三百二十八兆円ということであります。やはりそうである以上、この配当を無税で内部留保に積み上げるのではなくて、さらにしっかり課税を行って国民に再分配していくということが必要なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○麻生国務大臣 今、配当金につきましては、配当を支払う側の法人、例えば前の例を引けば、子会社の段階において既に法人課税が課されておりますので、先ほど宮本先生も御指摘がありましたように、二重課税を避けるという観点から、配当金を受け取る法人、親会社なんかの場合ですけれども、その段階では益金に算入しない、すなわち非課税にするというのは、これは基本的に伝統的な考え方であり、総じて先進国はこの考え方だと思います。ただし、単なる投資対象として保有するような持ち株比率の低い株式は、債券投資など他の投資とのバランスというものを考慮しなきゃいけませんので、少なくとも、部分的に課税するため、一部のみ益金不算入としておりますのは御存じのとおりです。二十七年度の税制改正では、課税ベースの拡大というものに取り組む中で、こうした考え方をさらに進めて、持ち株比率五%以下の会社からの配当などについては、現行の益金不算入の割合、すなわち非課税の割合を五〇%から二〇%に引き下げるなど、かなり抜本的な見直しを行ったところでもあります。先生の御主張は、会社の支配を目的とするような持ち株比率の高い株式からの配当にも課税すべきということなんだと思いますが、これにつきましては、支店の形態でも子会社の形態でも税負担は変わらないようにすべきだということを考えれば、やはり引き続き一〇〇%の益金不算入にすることの方が妥当だ、我々はそう思っております。
○宮本(徹)委員 今回、この制度の一部を見直して、課税強化の方向に踏み出したという点は、私たちも注目しているところであります。しかし、これによる増収の見込みは九百二十億円ということで、受取配当の益金不算入制度による減収額は一・四兆円ですから、是正されるのは数%ということになります。もうちょっとたくさん質問を用意していたんですけれども、質問時間がなくなってきましたのであれなんですけれども、先ほど来紹介している政府税調では、「資産運用の場合は、現金、債券などによる他の資産運用手段との間で選択が歪められないよう、適切な課税が必要である。」ということを言っております。そして、自民党の税調でも、支配目的が低い投資目的の場合については全額益金算入という案も提示されていたというふうに聞いております。そうであるならば、二〇%であれ、株式の配当だけを益金不算入にすると、株式投資だけが有利となり、選択をゆがめるというのは明らかです。選択をゆがめないためには、やはり全額益金に入れる、不算入割合はゼロ%にすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。二十七年度の税制改正におきまして、持ち株比率が低く、資産運用に近い株式というものの配当の取り扱いというのは、一つ議論でございました。この配当の扱いにつきましては、他の投資機会との選択に対しまして税制からバイアスを与えないようにするという観点から、益金不算入の割合を五〇%から大幅に引き下げることといたしましたが、持ち株比率が低くても支配目的が全くないとは言い切れない、あるいは益金不算入割合を余りにも大きく引き下げるその影響もあるのではないかというようなことから、二〇%の益金不算入という形にしたというところが現状でございます。
○宮本(徹)委員 諸外国を見れば、ドイツでは、持ち株比率一〇%未満の場合は全額益金に算入する、フランスでも、持ち株比率が五%未満の場合は全額益金に算入するということをやっているわけですから、自民党税調だってその案もあったわけですから、それはできないはずがないというふうに思います。この受取配当益金不算入制度見直しを引き続き求めたいというふうに思います。今回の法案は、法人税率の引き下げでも課税ベースの拡大でも、大企業、経団連の要求をほとんど丸のみした法案になっているというふうに思います。法人税率を引き下げ、大企業優遇を続けながら、消費税増税と赤字企業への増税で穴埋めしていくというのは許されません。本法案の撤回を求めて、私の質問を終わります。